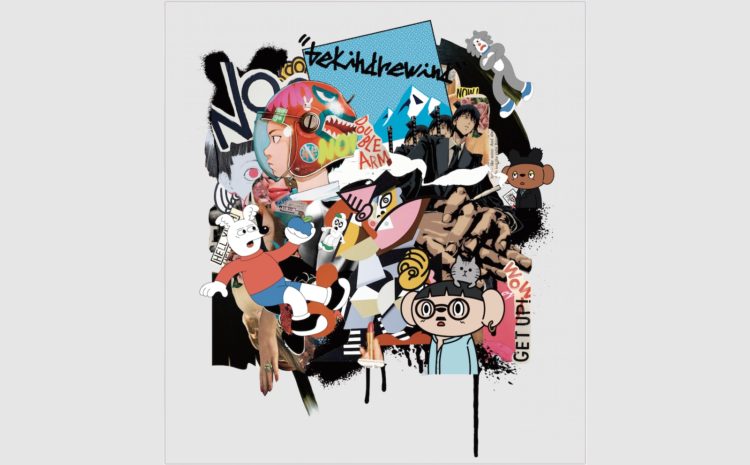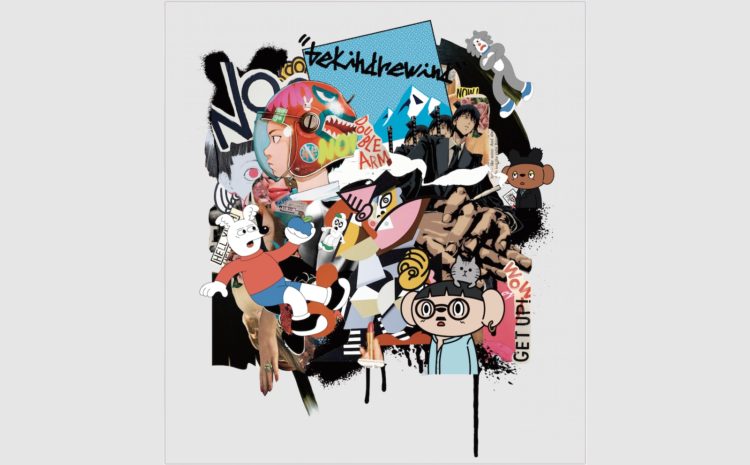Crew Kensho Onuki LONDON NITE / Music Critic


Kensho Onuki
保存
ー祝 近田さん特集ー LONDON NITE主宰 / 音楽評論家 大貫憲章《後編》
ー特集ー
LONDON NITE主宰 / 音楽評論家
大貫憲章
Interview By Yukiko Takeda
Photography By Yuichiro Nomoto
Direction By PROJECT ONE

(前編
・近田さんとの出会いは『anan』編集部。
共通点が多かった
・昭和・平成を代表する音楽家の一人。
楽曲にリスペクトしながら表現する凄さ
・音楽評論家の道を切り拓いた、
松山猛さんとの出会い
(後編
・ザ・クラッシュのアルバムツアーに密着。
それがDJを始めたきっかけ。
・藤原ヒロシ・高橋盾など、
カリスマに愛された『ロンドンナイト』
・ただ音楽が好き、現場が好きで40年続けてきた。それは近田春夫も同じ
・ライブハウス、クラブ、レコード屋。
渋谷は音楽の街

初めてロンドンを訪れたのは73年、大学4年の夏休みを2週間使って、フェスを見に行った。「ライブハウスはもちろん、本場の野外フェスが見たいと思って。当時流行っていたのがデヴィッド・ボウイやT・レックス、グラム・ロックが全盛。クイーンを初めて知ったのもその時です。その旅で何本か原稿を書きましたね」。その後、パンクを生で見たいと思い、76年に2度目の渡英。デビュー間もないザ・クラッシュのライブを見る。そして80年、3度目の渡英でDJの存在を知ることになった。
「80年にザ・クラッシュの『ロンドン・コーリング』のアルバムツアーがあると知り、これは取材できるんじゃないかと日本の担当者と2人で行きました。スケジュールは1週間の予定で、そのうち密着は3日間。同じ移動車に乗せてもらい、ミック(・ジョーンズ)がジョイントを巻いて、どう? って勧めてくれたりもあったね(笑)。
そのツアーで初めて知ったのがDJでした。バリー・マイヤースっていうDJだったんだけど、客入れの時に生で曲をかけていたのには驚きました。曲はレゲエだったんだけど、ヘッドフォンをつけてレコードをかけて、絵がとにかくカッコ良かった! どんな機材を使っているか興味津々で見ながら、日本に帰ったら自分もやろうと思いました」

『POPEYE』編集部の知り合いに相談すると、すぐに西麻布のショットバー『トミーズバー』を紹介され、DJができることに。「トミーさんが気さくな方で気軽にOKしてくださったんです」。そこで始めたDJが話題になり、新宿の『ツバキハウス』の店長 佐藤俊博さんから「うちでやらないか」と声をかけてもらったのが、ロンドンナイト の始まりだった。
「トミーズバーは50人、ツバキハウスは800人と一気にキャパが大きくなって、僕でいいんですか?と佐藤さんに聞いたんですよ。今と同じスタイルでいいんでと言ってくれて。だけどあまりにお客がいないから申し訳なくて、他のDJに変わってやってもらってた時があったんだけど、佐藤さんから『なんで大貫くんがやっていないんだ』とお店のスタッフが注意されたこともありましたね。『POPEYE』で宣伝してくれたり、ファッションページ担当の編集者がきてくれたり。スタイリストの大久保篤志くんとかもみんなで来てくれたけど、最初の半年とかは『暇だねえ』とか言ってガラガラだったんですよ(笑)」
それでも佐藤さんに「続けてください」と言ってもらえたと話す憲章さん。ロンドンナイトの歴史はここから始まった。
音楽好き・ファッション好きの口コミで、徐々にお客さんが集まるようになる。当時のディスコはフリーフード・フリードリンクで、カレーやスパゲッティ、冬はおでんなどが自由に食べられ、飲み物もカクテル系は飲み放題。踊って、お腹が空いたら食べて、また踊り、朝まで過ごす若者も少なくなかった。しかし82年に起きた歌舞伎町での死傷事件を機に深夜営業が規制されるようになる。ツバキハウスは87年に閉店、場所を変えてロンドンナイトは続いて行く。
「UNDERCOVERの高橋盾が来るようになったのは、88年とかですね。岩永ヒカルは、僕の運転手をやってくれていたんですよ。藤原ヒロシは、セツ・モードセミナーに入学する前、高校生の頃に伊勢からわざわざ遊びに来てたとか。ヒロシは、とにかくファッションが個性的で注目を集めていたよね。リーゼントに革ジャン、ボンテージパンツ、でも顔はかわいらしい感じで。女の子の中でも話題だったみたい。菊池武夫先生がお弟子さんを連れて来たこともあったね。ツバキハウスは、もともと文化服装学院や東京モード学園の子が多かったから、ファッションショーをやったりもしてました。僕が音楽を担当したこともあったね。




お客さんの3割くらいはかっ飛んだファッションをして、残り7割は街着の人。取材で紹介されたりすると、どうしても分かりやすい人の写真を撮るから、それを見てさらにそういう人が集まって来たんだよね(笑)」
当時の選曲は、ロンドンのロックとパンクがメインだが、音源が少ないため、エアロスミスやキッスをかけることも。洋楽中心だったが「実は歌謡曲も流してたんですよ」と大貫さん。ピンクレディー、サザン・オール・スターズ、違和感のない曲はどんどんかけて「とにかく自由だった」と振り返る。お客に、デビュー前の吉川晃司やチェッカーズなどが来たこともあった。
「正直なところ、40年も続くと思ってなかったよ。最初はガラガラだったしね。でも現場が仕事場で音楽が好きだったんだよね。現場が好きなのは近田も同じだと思う。あいつも現場主義で、ライブが好きだからね。近田が病気になった時、それこそ人生で一番辛かったと思う。内田裕也さんの自叙伝『内田裕也 俺は最低な奴さ』を近田が監修したりしていたから、それが重なっていたりもして、心残りもあったのかもしれないと思う。裕也さんの誕生日パーティーも近田が3年続けて音頭を取ってたしね。その後、高木完ちゃんに振って、その後(高橋)盾になったりもしたのかな」
ロンドンナイトに魅了され、そこから生まれた才能の数々。自分にとっての「ロンドンナイト が学校だった」と振り返るアーティストも多い。
「みんな才能の使い方が素晴らしいんだよね。独自だし、自分の中だけに閉じ込めないで、発信できる人間力がある。ロンドンナイトに来てそれが培われたのであれば素晴らしいことなんだけど、僕は入り口まで案内しただけだからね。自分で価値を決められると知ってくれればいい。“ロンドンナイト卒業”とか言ってくれる人もいるんだけど、僕にとっては学校じゃなくて、幼稚園か動物園(笑)。ケンカもあるし手を焼くことも多かったけど、それでも楽しかったし、そういうカルチャーが日本に実在したことも事実だし、自分にとってもいい時代だったと思う。でも僕は、その頃と全然変わってないんだよね。年だけとっちゃって、セブンティー(70歳)だけど気持ちはセブンティーン(17歳)なんだよね(笑)」。

人と時代に導かれながら、現在まで続くロンドンナイトは2021年に41周年、そして松山さんや石坂さんらとのご縁から始まった音楽評論活動も51年目を迎えた。今まで続けてこれた理由を「誰よりも音楽が好きで、ロックが好きだから」と嬉しそうに話す。音楽に導かれ、ロックの伝道者としての役割を担う生き方に、「大貫憲章」という人物がいかに音楽に愛された人物なのかを強く感じた。
大貫さんにとっての渋谷とは。渋谷西武や西武劇場、プラネタリウムなど、様々なスポットを挙げてくれたが、一番は音楽の街。90年代から2000年代にかけてレコードショップが次々にオープンし、クラブシーンを牽引するような店が登場したのが渋谷だった。
「渋谷といえば、宇田川町の『オルガンバー』ですね。須永辰緒が立ち上げた場所で、できた時にはすぐに行かなかったんだけど、ある時ふと行ってみたらすごくいいところで。古いビルで看板も出てないんだけど。あとは桜丘町の『THE ROOM』、ここはKYOTO JAZZ MASSIVEの沖野くんの箱で、東京の拠点。僕も何かやらせてもらいたいなと思って話を持っていって、GROOVY ROCK CARAVANというイベントをずっとやっていました。あとは、円山町の『クラブエイジア』かな。ここでもロンドンナイトをさせてもらいました。
今は『LINE CUBE SHIBUYA』に名前が変わったけど、渋谷公会堂では色々なライブを観に行ったね。デヴィッド・ボウイとか。渋谷は、僕にとってはやっぱり音楽の街。レコード屋とクラブ、ライブ会場。昔あったけど、今は無くなっている店もたくさんある。街の様子は大きく変わっているんだけど、音楽に根ざした街というは変わっていないんだよね」

保存