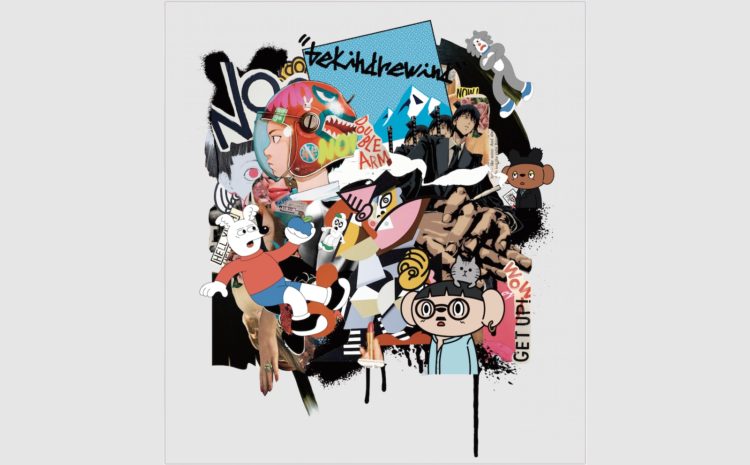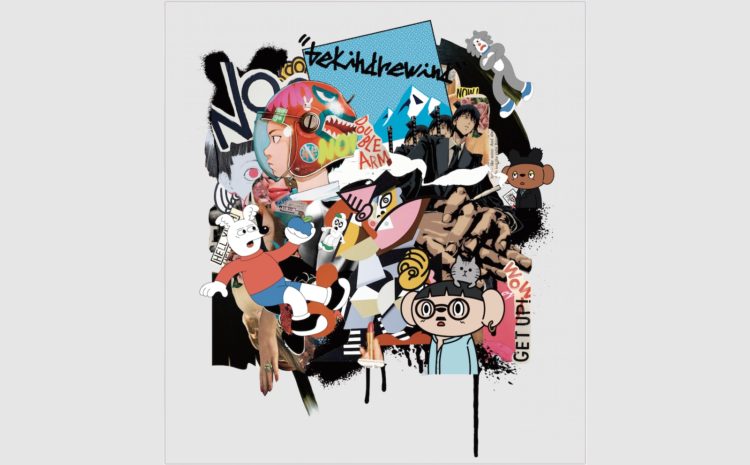Crew Kensho Onuki LONDON NITE / Music Critic


Kensho Onuki
保存
ー祝 近田さん特集ー LONDON NITE主宰 / 音楽評論家 大貫憲章《前編》
ー特集ー
Interview By Yukiko Takeda
Photography By Yuichiro Nomoto
Direction By PROJECT ONE

LONDON NITE主宰 / 音楽評論家
大貫憲章
10月16日、東京は新木場にあるageHaで、近田春夫の古稀と音楽生活50周年を記念したパーティ『 B.P.M. Syndicate』が大貫憲章、藤原ヒロシ、高木完、小泉今日子、イリア、TSUYOSHI SUZUKI、YOUTHEROCK★、ゆるふわギャング、HENTAI CAMERA、ブライアン・バートン・ルイスなどヴァラエティに富む、しかし確固たる共通点を持ったゲストを迎えて成功裡に終わった。年齢も、ジェンダーも、音楽ジャンルも、キャリアも、才能の方向も、多分、何もかも異なる彼らに一つ共通するのは、意味なく過去を振り返ることをしないで、未来へ向かう、新しいヴィジョンを映し出す活動を続けていることだといえる。

音楽好き・ファッション好きなら、大貫憲章という名前を聞いて知らない人はいないだろう。音楽評論家であり、40年に渡り続く伝説の日本初ロックDJイベント『LONDON NITE』(ロンドンナイト)を主宰、70歳を迎えた今も、ラジオやインスタライブで発信し続ける、音楽界のレジェンドであり重鎮である。
近田春夫さんの古希をお祝いするにあたり、大貫憲章さんに近田さんとの出会いや交流についてお話を聞いた。そこから派生し70年代、80年代のカルチャシーン、ロンドンナイトを始めたきっかけ、そこで出会った人たちとのエピソードを語ってくれた。ロックミュージック、ファッション業界に多大な影響を与えて来た人物でありながら、フラットで物腰柔らかな大貫さん。人との縁、時代に導かれたレジェンドが辿った足跡は貴重なヒストリー・アーカイブで、後世に残したい物語である。
(前編
・近田くんとの出会いは『anan』編集部。
共通点が多かった
・昭和・平成を代表する音楽家の一人。
楽曲にリスペクトしながら表現する凄さ
・音楽評論家の道を切り拓いた、
松山猛さんとの出会い
(後編
・ザ・クラッシュのアルバムツアーに密着。
それがDJを始めたきっかけ。
・藤原ヒロシ・高橋盾など、
カリスマに愛された『ロンドンナイト』
・ただ音楽が好き、現場が好きで40年続けてきた。それは近田春夫も同じ
・ライブハウス、クラブ、レコード屋。
渋谷は音楽の街

大貫さんが近田春夫さんと出会ったのは1970年、平凡出版社(現在のマガジンハウス)で雑誌『anan』編集部だった。
「大学1年の頃ですね。当時『anan』には“熊猫週報”という企画ページがあり、それを若い奴らが担当していて、編集部に若い連中がかなり多く出入りしてたんだよね。僕はそこで音楽やレコードの記事を書いていました。そこで近田くんに出会ったんです。話をしてみると音楽をやっていて、家が同じ世田谷で近い。年齢も一緒で、誕生日も3日違い。編集部で何をやってたかは分からなかったけど(笑)共通点がやたら多くて話は早かったよね」
編集部での交流はそれほどなく、近田さんのバンド、ハルヲフォンの活動を経て話すようになった。ハルヲフォンは1972年に結成、1975年にシングル『FUNKYダッコNo.1』でメジャーデビュー。当時のことで、今でも鮮烈に記憶に残っているエピソードがある。
「当時、等々力駅から玉川警察に向かう途中に、近田くんの自宅と事務所があった。そこにバンドの機材車がよく停まっていて、そのバンに『FUNKYダッコNo.1』のステッカーが貼られてたんですよ。そのステッカーがとにかくかっこ良くてね。まだその時は曲のことを知らなかったから、FUNKYダッコって何?って聞いたら、近田くんが僕に教えてくれたんですよ。そこからさりげなく曲の売り込みを受けて(笑)意識するようになりましたね」

「近田もすごく気を使う人なんですよ」と、ほど良い距離感を保ちながら、交流の中でお互いの信頼関係を深めて行く。
「近田は若い頃から喋るのは早いけど、人の前には絶対に入ってこない。押し引きがうまくて、嫌な感じが全然しないんですよね。やっぱり音楽の話をすることが多くて、1980年代後半、屋敷豪太くんが海外で活動をしていた頃にグラウンドビートが流行って。そのことについてイベント会場かどこかで近田と話したことがあって。それがお前のグラウンドビートの解釈ね、いいじゃん! と。褒めてくれたのかは分からないけど(笑)お互いに言わんとすることが分かって。作品を通してもだけど、本人と関係ないことや何かの拍子にふと話した時に、彼の音楽観や感覚を肌で感じることが多かったです」
ハルヲフォンのセカンドアルバム『ハルヲフォン・レコード』のライナーノーツは大貫さんが寄稿した。バンド活動や作曲家、音楽プロデューサーなど、近田さんの多岐にわたる活動から大貫さんが一番評価しているのは音楽家としての才能だ。功績は大きく、昭和・平成を代表する人物の一人でもあると讃える。

「彼は洋楽的な音楽をやっているけど、歌謡曲というジャンルの中で、どう役割を果たすか、そんなことをいつも考えていたんじゃないかと思って。洋楽思考のロックバンドは、キャロルとかフラワー・トラベリン・バンドとかいっぱいあるけど、それとは違う。あくまで歌謡曲ベース、流行歌ベースでやっている。演奏は洋楽なんだけど歌謡曲でもあるから、どんなカバーをやってもぴったり合うんだよね。
『東京物語』を初めてライブで聴いた時、すごくカッコ良かったんだよね。ディープ・パープルみたいなんだけど歌謡曲でもあって。これ、実は森進一の曲なの。同じ曲だけど完全にロックなんですよ。こいつは天才だな、と思いましたね。洋楽を歌謡曲に取り入れたのは近田が最初とは言わないけど、その功績は本当にすごいなと。昭和・平成を代表する日本の音楽家の一人だと思ってます。表現力や解釈力、伝統を踏襲しつつリスペクトを忘れずに表現することの凄さを今でも感じ続けてます」
大貫さんの音楽評論家としてのキャリアは、雑誌『anan』での執筆から始まった。当時の『anan』編集部は、スタイリストの高橋靖子さんを始めとする若き文化人の溜まり場だった。作詞家の松山猛さんと出会ったのも編集部で、彼から手ほどきを受け音楽評論家としての人生が始まった。
「音楽の仕事がしたいの? 『ミュージック・ライフ』とかでやりたい?と聞かれ、はい、やりたいです!と言うと、編集部に連れてってくれて。できる奴だからと紹介してくれて、いろいろな編集者とつないでくれました。松山さんの紹介だからと、とんとん拍子に仕事が決まっていき、最初は50字くらいだったのが、次800字。次は見開き2ページになって。
松山さんはレコード会社にも連れて行ってくれ、東芝EMIに行った時には、洋楽担当のボスだった石坂敬一さんを紹介してくれて。石坂さんは後に日本レコード協会の会長になる人なんだけど、その時石坂さんから、君は名前が読めないねと言われて。じゃあ“憲章”だな、と。当時テンプターズにショーケン(萩原健一)がいたので、君はケンショー(KENSHO)ね、と。それで“大貫憲章”になったわけ」

1970年代の『POPEYE』創刊時はアメリカ・カルチャーが主流で、スケートボード、ポロシャツ、ナイキのスニーカー、キャンプギアなどが誌面に並んでいた。イギリスの情報がないため、大貫さんは自分でロンドンの情報を探した。レコード会社に行くと置いてあるイギリスの音楽情報誌を見たり、青山ブックセンターで海外の音楽雑誌を購入したり。ミュージシャンのファッションや宣伝記事を見て、「今のロンドンはこんな感じなんだ」と知った。レッド・ツェッペリンやディープ・パープルなどが人気を集める中、75-6年にはパンク・ロックが登場する。
保存